SITE CONTENTS
Purchase
買いたい
Renovation
リフォームしたい
暮らしの質を進化させる住まいづくり
私達は、工務店でもあり不動産屋でもある特色を活かし、
土地探し、資金計画の段階から、建築計画、施工、
アフターメンテナンスと持てる知識を存分に活かした
住まいづくりをご提案します。
暮らしの質を進化させる
住まいづくりでお客様に
快適/安心/健康
をお届けします。
Special Site

上質に包まれる空間の家
Updated date : 2026.02.09
#アイランドキッチン#ファミリークローゼット#ホテルライク風
WORKS
制作実績多数!理想の住まいを実現! 創業以来多数の家族の家づくりの夢を叶えてきた森下技建。 その実績の一部を抜粋してみたので、住まいづくりの参考に 是非見てほしい。
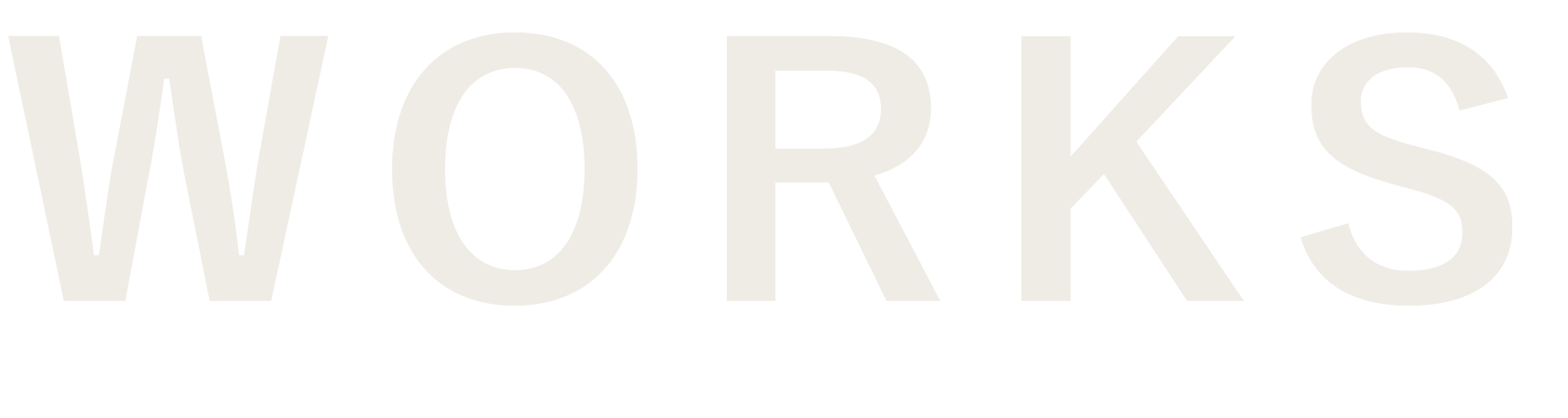

新築住宅(自社物件)
Updated date : 2025.11.26
#2階リビング#インナーガレージ#ホテルライク風

Updated date : 2025.04.24
#2世帯#ウォークインクローゼット#スタイリッシュ#タイルデッキ

新築住宅(自社物件)
Updated date : 2025.04.24
#モダン#ロフト#化粧柱#化粧梁

新築住宅(自社物件)
Updated date : 2025.04.24
#シューズクローゼット#モダン#石目調フロア

新築住宅(自社物件)
Updated date : 2025.04.23
#アイアン手すり#ひな壇階段#ホテルライク洗面台#ホテルライク風

新築住宅
Updated date : 2024.12.17
#3階建て#ホテルライク洗面台#ホテルライク風#石目調フロア

新築住宅(自社物件)
Updated date : 2024.11.17
#スカイバルコニー#モダン#木目調

新築住宅(自社物件)
Updated date : 2024.11.14
#ナチュラル#ハイドア#モダン#木目調
TAGS

森下技建は、羽曳野市を中心に一戸建ての新築、店舗・共同住宅などのリフォームの施工を行っている地域密着型の工務店です。
注文住宅からリノベーションまで、様々なニーズに対応し、お客様ひとり一人の豊かな暮らしを叶えます。
家づくりを通して、ご家族様との暮らしを大切にし、快適で円滑な打ち合わせができるよう、想いに寄り添った対応をいたします。
SPEC
森下技建では、注文住宅やリフォームを通じて、ご家族様の幸せな暮らしをつくるため、豊富な商品ラインナップをご用意しております。
お客様ひとり一人の「想い」に寄り添い、豊かな暮らしを叶えます。
HOUSE BLOG
一戸建ての注文住宅や店舗・共同住宅などのリフォームについて役に立つ情報を配信していきます。
当社は、お客様のこだわりやご要望に沿った自由設計を基本に注文住宅を建てさせていただきます。
FAQ
お客様からよくいただくご質問を集めました。
森下技建の家づくりについて、気になることがございましたら、ぜひこちらをご覧ください。
森下技建の施工エリアは、大阪府大阪市羽曳野市をはじめとした大阪府全域で行っております。
細かい寸法調整から独創的なデザインまで、お客様のご希望に柔軟に対応可能です。
1mm単位の調整や、直線にこだわらない設計も可能ですので、理想の住まいを一緒に実現しましょう。
住まいに関するお悩みやご要望を、経験豊富な設計士に直接ご相談いただけます。
気軽にご参加いただけますので、ぜひご予約の上ご来場ください。
「資料だけ欲しい」というお客様は、資料請求フォームにその旨をご記載ください。
お客様のご意向に沿った対応をさせていただきます。
当社では、木造軸組工法による住宅を提供しております。
鉄骨造にも対応可能です。

ABOUT
羽曳野市に地域密着の工務店「森下技建」です。
当社は羽曳野市を中心とし、一戸建ての新築・リフォームなど住宅に関する工事を承る工務店。
数多くの施工実績と商品ラインナップでお客様の理想の家づくりを心がけています。
お客様と快適で円滑な打ち合わせができるよう、想いに寄り添った対応を行い、
最適なプランをご提案するのも当社の大きな特徴です。
羽曳野市周辺で一戸建て新築・リフォームに強い工務店をお探しなら、
地域密着の工務店「森下技建」へお任せください。

PRESENT
森下技建の施工がよくわかる資料をプレゼントいたします。
まずはお気軽にお問い合せください。